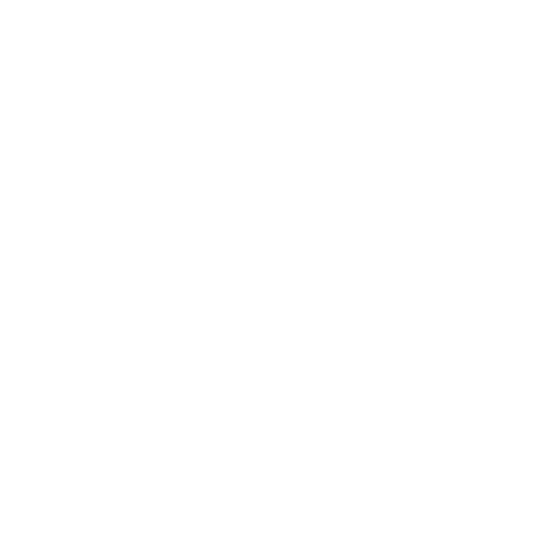命のスペシャリスト「助産師」の叡知を届ける──With Midwifeが描く社会インフラとは
Startup Vision Interview #8

命のスペシャリスト「助産師」の叡知を届ける──With Midwifeが描く社会インフラとは
STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、With Midwifeの岸畑氏のインタビューをお届けします。 現代の企業が直面する人的資本経営の課題に、新たなアプローチで挑む事業がある。With Midwife代表の岸畑聖月氏は、助産師としての専門性を活かし、従業員の「見えづらい悩み」をケアする企業向けサービス『THE CARE』を展開している。不妊治療、メンタルヘルス、育児といった個人的な課題が、実は企業の生産性や離職率に大きく影響することに着目。社会性と資本性を「翻訳」することで、企業の持続的成長と社会課題解決の両立を目指す同社の挑戦、そして背景に流れる事業哲学に迫る。
インタビュイー

1991年生まれ┃14歳の闘病の経験から助産師を志し、京都大学大学院医学研究科に進学。卒後年間約2,500件のお産を支える総合病院で助産師として臨床経験を積みながら、2019年株式会社With Midwife( https://withmidwife.jp/ )を創業。
人的資本経営に資する女性活躍や健康経営を包括的にサポートする、健康と子育ての従業員支援プログラム「The CARE( https://thecare-biz.jp/ )」を展開し、伊藤忠商事株式会社やロート製薬株式会社など全国的に導入が進んでいる。またこども家庭庁大綱における検討会の有識者や、関西エリアの女性起業家支援事業( https://discovermyself.jp/ )のプロジェクトマネージャーも務める。
ミッション
興味関心
STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、With Midwifeの岸畑氏のインタビューをお届けします。
現代の企業が直面する人的資本経営の課題に、新たなアプローチで挑む事業がある。With Midwife代表の岸畑聖月氏は、助産師としての専門性を活かし、従業員の「見えづらい悩み」をケアする企業向けサービス『THE CARE』を展開している。不妊治療、メンタルヘルス、育児といった個人的な課題が、実は企業の生産性や離職率に大きく影響することに着目。社会性と資本性を「翻訳」することで、企業の持続的成長と社会課題解決の両立を目指す同社の挑戦、そして背景に流れる事業哲学に迫る。
「命の空白地帯」に気付いた14歳の原体験
- インタビュアー
- まずは、With Midwifeを創業するに⾄ったエピソードからお伺いできますか?
- 岸畑
-
出産を支える、ひいては、目の前にある命もそうではない命も含めて「救う側の人間になりたい」と強く思ったのは、14歳のときの闘病がきっかけです。婦人科系の疾患で、将来妊娠や出産ができない身体になりました。女性は結婚して出産するのが普通だと思っていたのが、自分自身が子どもを産めなくなったことで「不妊」というものの存在を知ったんです。私にとってはすごく大きな体験でした。
病気自体も衝撃的な出来事ではあったのですが、マインドチェンジをもたらしたのは両親の悲しむ姿でした。父は「産める身体に産んであげられなくてごめん」と訴え、母は私にずっと寄り添ってくれました。そんな両親を見て、心配をかけたくないと思いましたし、「この経験を、何かポジティブなものに変換できないか?」と考えたんです。この時に「ああ、自分が救う側の人間になろう」という思いに至りました。これが創業へつながる原体験の一つです。
- インタビュアー
- 14歳という多感な時期に、そのような深い体験をされたのですね。
- 岸畑
-
実は原体験はもう一つあって、自宅療養中にネグレクトを発見したことです。家のすぐ近くで赤ちゃんの泣き声が聞こえ、そのお家にいくと、赤ちゃんを置いたまま両親が出かけてしまっていました。私はすぐにはその大変さに気づきませんでしたが、大人たちの会話を聞いて、「これば重大な問題だ」と気づきました。
大人たちは口々に放置してしまった母親を批判しましたが、私自身は「私は産み育てることができないが、この人は妊娠して産むことを成し遂げた。なのに、なぜお母さんだけが責められるんだろう。こうなる前に、もっとできることがあったのではないか。」と思いました。この体験が「医療の手前のケア」の領域で人のサポートをしたいという思いにつながっています。

- インタビュアー
- それから助産師の道に進まれたとのことですが、もともと起業も視野に入れてキャリアを選択したのですか?
- 岸畑
-
起業することは学生時代から考えていました。なぜなら、現在の病院や行政の支援体制では、命にまつわる社会課題が解決されていないからです。課題解決のためには新しい仕組みを作らなければならない。それはきっとビジネスという形になるだろうと考えていました。そこで大学院では助産学と経営学を学び、臨床の現場に入りました。
私が所属する病院は関西で一番出産件数が多く、多様な症例を目の当たりにしました。それはまさに、現場で起きている社会課題そのものでした。
- インタビュアー
- 実際に、どのような現場を目の当たりにしたのでしょう?命の最前線に立つ中で、今の事業につながる印象的なエピソードを伺えますか。
- 岸畑
-
印象的だったのは、妊娠19週で中期中絶を選択された40代の女性のケースです。その方は長期の不妊治療の末にようやく妊娠を果たしたのですが、羊水検査で胎児に障害があることが分かりました。生まれたとしてもすぐに死ぬわけではない、でも、医療ケアが必要になる。ものすごく葛藤したと思います。
結果、その方は中絶を選択しました。妊娠12週を超える中絶は、陣痛誘発剤を使って通常分娩することになります。誘発剤を投与し陣痛を待つ間に、ご夫婦と私は赤ちゃんのお葬式の準備や、記念のカード作りをして過ごしました。途中からは笑顔も見られ、「こんなに幸せな出産になるとは思わなかったです」と彼女は言ってくださって、温かい印象でご出産されたんです。その後勤務の都合で、私とその方はお会いすることはできませんでした。
ところが、2、3ヶ月後に偶然街で再会した際、彼女は突然号泣しました。職場復帰後の産業医との面談で、中絶の経緯を根掘り葉掘り聞かれたとのことでした。「自分が悪いことをしたみたいな意識が芽生え、すごく苦しい」と彼女は私に打ち明けました。この時私は、「多様な命に向き合う女性が職場にいるのに、そこを支援する医療者でさえ、その感覚なんだ。ケアのスペシャリストがいないんだ」と強く感じました。こうした気づきが今の事業につながっています。
見過ごされた社会の構造問題

With Midwifeは「生まれることのできなかった、たったひとつのいのちでさえも取り残されない未来」をビジョンに掲げる。そこには、岸畑氏が直面してきた「制度の隙間にある命にまつわる様々な事情」に対する配慮が込められている。「仕組みを変えなければならない」と話す岸畑氏の目には、今の社会の構造問題がどのように映っているのだろうか。
- インタビュアー
- 産後うつや虐待、“孤育て”など、表出した社会課題の裏側には、どのような構造問題があると思いますか?
- 岸畑
-
まず社会保障という点で言うと、大前提として生きている人が対象になるので、失われたものには目が向きにくい仕組みになっていると思っています。生命がある方や障害がある方への社会保障は行き届いていますが、亡くなった後や、「子どもが欲しい」と願う気持ちのような、目に見えない部分を支援することは難しいのです。さらに、民間サービスの場合はもっとドライで、購買能力があるか(お客さんになり得るか)が重視されます。
子育てというところにだけ焦点を当てると、「不可逆であるがゆえに見過ごされてしまう」ことも構造問題につながっています。子育てにまつわる悩みは、一度過ぎ去ってしまうと、その辛い瞬間は二度と戻ってきません。昨日の困ったことと今日の困っていることは違いますし、子どもの成長段階に応じて悩みは変わっていきます。このように不可逆的だからこそ、「この領域」の、「この課題」を解決するために本腰を入れて取り組もうとする人がなかなか現れないのだと思います。
さらに助産師という分野で切り取ると、助産師の活動場所が病院に限定されたことが問題です。かつて第二次世界大戦が終わる頃までは、助産師は地域に根ざして活動する専門職でした。出産だけでなく、妊娠中のケア、子育て、性教育、女性や家族の話を聞くなど、命の営み全般にわたる支援をしていました。しかし、戦後GHQの命令で自宅出産が抑制され、出産が病院中心になったことで、助産師の役割が病院内に限定されてしまったんです。出産介助を中心にその他の支援を行っていた助産師にとって、活動場所が病院のみになることは、命の営み全般のケアができなくなることを意味します。結果的に、産前教育やメンタルヘルスも含めた女性の健康管理、性と生殖に関する健康管理、育児支援などの周辺課題が取り残される状況が生まれたと思っています。

- インタビュアー
- 助産師が本来持っている、産前産後を通じた幅広いケア機能が、今の日本では十分に活かされていないということですね。
- 岸畑
-
おっしゃる通りです。特に日本の助産師はダイレクトエントリーではなく、看護師の資格もないといけないので、健康やメンタルヘルスにも明るく、世界的にみても能力が幅広いのです。だからこそ、私たちは助産師が提供できるケアを、病院外のコミュニティに広げることに挑戦しています。ただし、機能するコミュニティには「質量」や「粘着性」を高める構造や仕組みと、熱量を持った中心人物が必要です。
ところが現在の地域社会は、構造自体が希薄化しています。昔は婦人会や自治会のような構造があり、回覧板があり、そこにいわゆるコミュニケーターとして命の営みを一手に引き受けていた熱量の高い助産師がいました。それが今では、会合や自治会のような構造がなくなり、情報取得も個人ベースになりました。主体的に地域を動かそうとする人も減っています。このように希薄化した構造の中に役割を投下しても、おそらく機能はしません。
私は現代社会でコミュニティとして一番機能しやすいのは「会社」だと思っています。人事名簿や組織構成など、確かな構造があります。そこに対して、働きやすさ、心地良さ、心理的安全性などウェルネス・ウェルビーイングの考え方を、『THE CARE』のウェルネスコーディネーターたちが熱量高く掲げて、企業というコミュニティを粘着性の高い状態にアップデートできたらと思い活動しています。
見えづらい悩みを可視化する『THE CARE』の仕組み

With Midwifeが企業に対して提供するサービス『THE CARE』は、不妊治療、メンタルヘルス、ハラスメント、子育て、更年期など、従業員が抱える「見えづらい悩み」にフォーカスする。同社の調査によると、これらの悩みは個人の問題だけにとどまらず、望まない離職や生産性の低下につながり、出社しても生産性が低い状況をそのままにすることで、従業員1人あたり年間約56万円もの損失を企業にもたらしているという。また、育児離職による年間6,300億円もの経済損失推計や、女性管理職比率の引き上げ、男性育休取得率の向上が採用競争力に直結するなど、従業員の「見えづらい悩み」のケアが、企業の持続的成長や競争優位性に深く関わる経営課題であることが指摘されている。
- インタビュアー
- 『THE CARE』は、伊藤忠商事や阪急阪神不動産、タカラベルモントなどの大企業を中心に導入が進んでいます。具体的にはどのようなサービスを提供しているのですか?
- 岸畑
-
『THE CARE』は、望まない離職や生産性の低下を防ぐために、従業員の方々の個別サポートを行うサービスです。具体的には個別サポートができるアプリケーションと、企業専属の専門家(助産師)の提供を行っています。いわゆる外部相談窓口の立ち位置ですが、弊社独自の強みが3つあります。
ひとつは、専門家の質の高さです。助産師であれば誰でもいいというわけではなく、ライセンスを設けて質の高い専門職を育成・派遣する仕組みがあります。「質の高さ」の中には、医療支援はもちろん、キャリアや人事・労務支援など、企業経営目線でのアドバイスができる能力を含みます。ライセンスを持つ助産師は「ウェルネスコーディネーター」と呼んでいます。
二つ目は、ウェルネスコーディネーターを企業に専属配置している点です。いわゆるコールセンター型の運用ではなく、1社につき3名以上が専属で支援し、24時間365日、従業員の方々のあらゆる相談に応えています。この体制は、組織の粘着性を高めるために重要です。支援を受ける従業員の方にとっては、相談相手が自分のこと、自分の環境(会社)のことを理解してくれているかどうかの影響は大きいと思います。例えば不妊治療の相談の場合、通常の外部相談窓口であれば、気持ちに寄り添ってはくれるものの、不妊治療のおおまかな内容やよくある両立の悩み事の解決策をお伝えするにとどまるケースが多いです。弊社のウェルネスコーディネーターは所属先の会社の社風や繁忙期、独自の制度や方針なども理解しながら、個別最適化した支援ができます。「治療をしながら働くためには、社内のこんな制度が使えます。卵子凍結であればこんな補助があるけれど、あなたのキャリアの希望や落ち着いたタイミングを見計らうなら、今はこれをしておいて、具体的な妊娠は1年後を目安にトライしませんか?その間はお仕事を頑張りましょう」というふうにです。多くの方は不妊治療のプロでもなければ、キャリアのプロでもありません。キャリアとライフイベント、ヘルスケアを交えた意思決定は一個人では難しい。そこに専門家として伴走支援する体制は重要だと思っています。
三つ目の強みは、従業員の方々の「生の声」をデータ化し、人事や経営者に対し組織改善に向けた具体的な提案ができることです。「こういう相談があるので、こういう施策を打った方が良い」「こういう研修が組織改善につながる」など、踏み込んだ支援を行ったからこそできた提案も多いです。最近では、サーベイも広く活用されていますが、定量データだけではなく、定性的な情報にこそ重要な声が潜んでいることが多いです。

- インタビュアー
- これまで見過ごされてきた「声なき声」を拾うところに『THE CARE』の本質的な価値があるように思います。差し支えない範囲で、具体的な相談内容や解決方法の事例を教えていただけますか?
- 岸畑
-
育休復帰後の30代の女性からメンタルのご相談がありました。もともと育休期間中に、産後うつになっていた方でした。一旦は改善したものの、仕事復帰をして業務上の役割が増えたことや、夫がうつになったことで家事育児役割の比重が増し、メンタルの不調が悪化していました。実はこの方の産後うつは、子どもの相手が苦手というところから来ていました。家にこもって子育てをするよりも、外で仕事をしている方が気持ちが楽だったんです。だからメンタルの不調を職場に打ち明けることができず、産業医の面談でも「気づかれないふり」をしていました。我慢して隠し続けた結果、どんどん状態が悪化し、自傷行為や子どもに手を上げるまでになり、そのタイミングで『THE CARE』が導入されたことでご相談をいただきました。産業医面談も受けていましたが上記理由で支援にはいたらず、訪問看護や行政保健師も介入しましたが、担当者と折り合いが悪く「来なくていい」と突っぱねていたそうです。
このような状況に対し、私たちは「この人から働くことを取り上げてはいけない」と判断しました。休職させたら、おそらくこの方は命を絶ってしまう。そこでウェルネスコーディネーターは慎重に関係性を構築しながら、本人に専門職としての情報提供を行い、精神科の受診の再開や行政支援などを受けながら仕事を継続する提案をしました。行政には弊社から連絡する形で連携し、保健師さんの介入をはじめ、育児負担を軽減する支援を行いました。するとその方は支援を受け入れてくれるようになり、どんどん快方に向かっていきました。この事例は企業・行政の支援からこぼれ落ちてしまっていた「声なき声を拾う」という観点でとても印象に残っています。
社会性と資本性の間での「翻訳」

「その他にも事例は膨大にある」と話す岸畑氏。かつての地域社会で命を見守る存在だった助産師(産婆)の潜在能力を、企業というコミュニティの中で、人的資本経営の文脈で蘇らせようとしている。しかしそこには難しさもあると言う。
- インタビュアー
- 事業を推進する中で見えてきた課題はありますか?
- 岸畑
-
社会性と資本性の間で価値を「翻訳する」ことです。私たちの事業の本質は「命を救うこと」ですが、それを資本主義の文脈で説得力のある指標に落とし込むことにチャレンジしています。女性管理職比率の向上や、人的資本経営の情報開示による株価への影響、男性育休の取得率向上などがその例です。
難しいのは、社会性と資本性では見ている時間軸が全く違うことです。例えるなら、資本主義は「10cmの物差し」で日々の成果を測り、社会意義は「1kmの物差し」で遠い未来を見据えています。資本主義では長くても1年で成績がつき、上場企業なら3ヶ月ごとに株主説明が必要で、社内では月次、週次、場合によっては日次で成果を評価し、改善や継続の判断を行います。一方で、私たちが向き合うような社会課題は何年もかけて解決していくものです。
結局のところ、経営者の方がどこまでの未来を見据えて意思決定しているかによって価値基準は変わります。資本主義の中で、中長期的な社会貢献の価値を示すのは難しいですが、「翻訳」をして明確な指標に棚卸しできれば、これまで支援が届かなかった領域にも光を当てられると思っています。
- インタビュアー
- そうした「翻訳」の難しさがある中で、実際にサービスを必要とされている方々に、どのようなメッセージを伝えたいですか?
- 岸畑
-
私が経営者の方にいつもお願いしているのが、企業のコミュニティを作るルールメーカーとしての視点を持っていただきたいということです。ある種、経営者が好きなようにルール設定できるからこそ、できるだけ長い時間軸で価値を見定めて判断していただきたい。僭越ながら、いつもそう願っています。
従業員の方については、日本は地政学的に島国なので「自分たちでどうにかしなければ」という意識がすごく強いんですよね。家社会の範疇から外れると島流しになってしまうような文化があるので、「相談してね」と言っても、そのハードルは私たちが思っている100倍くらい高いんです。
でも、サービスを受ける側の方には、あなたを本気で支援したいと思っている専門職が、私たちだけでなく病院にも行政にも民間事業者にもたくさんいることを知ってほしいんです。簡単には出会えないこともあるかもしれないけれど、諦めずにSOSの手を伸ばし続けてほしい。
先ほどお話した事例の方も、最初は企業にも行政にも医療機関にも助けを求めることを諦めていました。そこから信頼関係を築いて、もう一度支援を受け入れてもらうまでに時間がかかりました。「受援力(助けを受ける力)」を高めることも、現代人の必要なスキルなのかもしれません。
2030年に「年間100万回のケア提供回数」達成を目指して

With Midwifeは事業の中期目標として「2030年に年間100万回のケア提供件数達成」というKPIを掲げ、社会性と資本性の翻訳を自らも実践しようとしている。
私たちは「命にコミットする回数をどれだけ増やせるか」を会社全体の定量目標として追いかけています。2030年に年間100万回のケア提供を目指すために、『THE CARE』の契約社数、一社あたりの相談利用率、売上、従業員数などの目標を全て連動させて設定しています。
- インタビュアー
- 『THE CARE』のサービスを、より多くの人や組織へと届けていくために、どのような人や組織とのつながりを広げていきたいですか?
- 岸畑
-
やはり人が集うときには何かしらの指標が必要だと思うのですが、円やドルに換算しやすい数字よりも、本質的な価値を共有できる方との出会いを大切にしたいですね。そういう方とは、直接的なビジネスの契約や資本提携といった短期的な関係には至らなくとも、中長期的な応援者として、一緒にビジョンを信じて、必要な時に力を貸したり、貸してくれるような関係を築きたいです。もちろん、お仕事として協力することもあると思いますが、そうでなくても一緒に何かを生み出していけるような出会いがあると嬉しいですね。
そのためにはきちんと発信していかないと、そういう方々に出会うこともできませんから、しっかりと情報を届けていきたいと思っています。
With Midwifeが目指すのは、現代社会が抱える「命の空白地帯」を埋め、企業の人的資本の動力を最大化し、ひいては社会全体のウェルビーイングを高める新たな社会インフラの構築だ。岸畑氏の深い原体験から生まれた情熱と、社会性と資本性を「翻訳」するロジック。岸畑氏が創る新たな社会インフラは、きっと日本の未来を明るく照らすだろう。
こちらの記事はに公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。