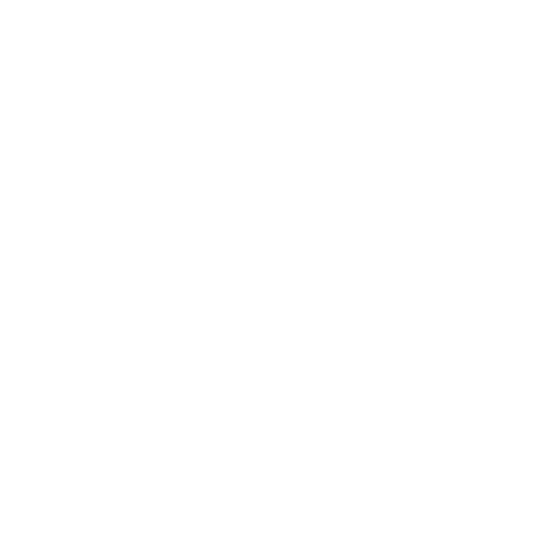母になった技術者が見出した、ロボットの新たな使命——キビテク・林まりか氏が描く共生のテクノロジー
Startup Vision Interview #5

母になった技術者が見出した、ロボットの新たな使命——キビテク・林まりか氏が描く共生のテクノロジー
STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、キビテク代表取締役CEOの林まりか氏のインタビューをお届けします。 かつて、工場の自動化は大企業の特権だった。しかし、労働力不足が深刻化し、中小企業でもロボット導入が避けられない状況となる中で、新たな課題が浮上している。ロボットを導入したものの、運用・管理に専門知識が必要で、結果的に現場の負担が増えてしまうケースが少なくない。 2011年に創業されたキビテクは、こうした課題を解決すべく、ロボット用の遠隔管理システム「HATS」を開発。メーカーを問わず様々なロボットを統合管理できるプラットフォームとして、物流・工場の自動化現場で着実に導入が進んでいる。未踏クリエーター出身の林まりか氏が、出産を機に芽生えた社会的視点から描くロボット技術の未来とは。技術者の純粋な好奇心から始まった挑戦が、いかにして人類の未来を変える使命に昇華されたのか。
インタビュイー

当社はロボット開発に強みのある会社です。創業以来、百数十件以上のロボット開発を行ってきています。そこで培った技術を活かし、ロボットの遠隔制御サービスと、それを搭載したロボット製品をご提供しています。
当社は事業を通して格差等の社会問題の低減に貢献することを目指しています。 お客様の課題の解決を行うことで、ロボットの普及に貢献し、社会の変容を積極的に推進します。 また、ロボットの遠隔オペレータという新しいテレワークを創り、在宅を余儀なくされている方や貧困地域の方等にとっての就業機会を増やし、機会の均等化を推進します。
ミッション
興味関心
STORIUMが応援するスタートアップの魅力に光を当てるストーリー。今回は、キビテク代表取締役CEOの林まりか氏のインタビューをお届けします。
かつて、工場の自動化は大企業の特権だった。しかし、労働力不足が深刻化し、中小企業でもロボット導入が避けられない状況となる中で、新たな課題が浮上している。ロボットを導入したものの、運用・管理に専門知識が必要で、結果的に現場の負担が増えてしまうケースが少なくない。
2011年に創業されたキビテクは、こうした課題を解決すべく、ロボット用の遠隔管理システム「HATS」を開発。メーカーを問わず様々なロボットを統合管理できるプラットフォームとして、物流・工場の自動化現場で着実に導入が進んでいる。未踏クリエーター出身の林まりか氏が、出産を機に芽生えた社会的視点から描くロボット技術の未来とは。技術者の純粋な好奇心から始まった挑戦が、いかにして人類の未来を変える使命に昇華されたのか。
技術者の好奇心から、未来世代に対する思いへ——出産を経て変化した事業への原動力

- インタビュアー
- キビテク創業のきっかけを教えてください。
- 林
-
2010年度のIPA未踏事業がきっかけです。当時は「人同士の触れ合いをセンシングする技術」の研究に取り組んでいました。私はメーカーの研究所に勤めていて、共同研究者の吉川さんは東大の研究室の講師をしていました。
未踏事業をプライベートな時間を使って行う中で、石黒先生(大阪大学のアンドロイドで有名な石黒浩教授)からの評価をいただき、「このメンバーで一緒に仕事をしたい」という思いが芽生えました。先輩の起業家たちの姿を見て「こういう道もある」と背中を押されたのです。
ただ、創業当初は明確な事業構想があったわけではありません。これは反省点でもあるのですが、純粋に「このメンバーで仕事したい」「自分たちが構想したものを社会に出すところまで、自分たちの手でやりたい」という思いだけで起業してしまいました。
- インタビュアー
- 現在の事業モデルが確立するまでには、どれくらいの期間を要したのでしょうか。
- 林
-
創業から現在の事業モデル確立までには約7年の歳月を要しました。その間に2つほどの事業にトライしましたが、うまくいきませんでした。正直、迷いの連続でした。一方で、ロボット開発の受託事業を継続的に行っていたことが、後の事業の基盤となりました。
決定的な転機となったのは、私の出産でした。それまでは技術者の好奇心を原動力に、自分たちが思いついた新しい技術を世に出したいという動機が中心でした。しかし出産を機に、まっさらな目で社会や世界を見る機会が増え、社会性の視点が私の中で強まりました。
子供と一緒に世界を見るようになって、子供に対する共感を大切にしたいという気持ちが高まりました。そして気づいたのです。ロボット技術で困っている状況にある子供たちを助けたい、未来世代が抱える問題を解決することにつながることをやりたいと思いました。
母親になって初めて理解したのは、技術は目的ではなく手段だということでした。長期的な影響があることを考えると、未来世代が困るであろうことは命に関わる話だと思いました。それはつまり、戦争か貧困の問題です。
- インタビュアー
- 貧困という課題から、なぜロボット技術にたどり着いたのでしょうか。
- 林
-
戦争と貧困という2つの課題のうち、検討の結果、貧困の問題に焦点を当てることを選びました。特に、自動化による労働の代替が加速していく未来を見据えての判断でした。
自分たちがやってきた自動化開発は、まさに工場を自動化するような取り組みでした。労働が代替されていく現実を目の当たりにする中で、資本主義社会は格差を内包していることに気づきました。技術の進化によって一部の人だけが恩恵を受けるのではなく、社会全体がアップデートされる可能性があると考えました。
そこで、ロボット技術による労働代替を単に効率化として捉えるのではなく、格差拡大を防ぎ、より持続可能な社会を実現するための手段として再定義しました。ロボットのオペレーターという新たなテレワークが普及すれば、在宅を余儀なくされている方や貧困地域の方等にとっての就業機会を増やすことにつながり、機会の均等化が進みます。工場や物流の現場で人間とロボットが最適に協働するシステムを構築することで、技術の恩恵を広く社会に行き渡らせる。それが私たちの新しい使命となったのです。

人間とロボットの理想的な協働を実現するプラットフォーム
現在のキビテクの主力サービスは、クラウドベースのロボット管理システム「HATS(ハッツ)」だ。遠隔管理・制御機能だけでなく、複数台のロボットを連携させるフリート管理機能も備えている。
HATSの最大の特徴は、メーカーを問わず、さまざまなロボットに対応できる汎用性にある。このシステムの背景には、展示会で華々しく披露されるロボットと、実際の現場で必要とされる機能との間に横たわる深い溝があった。

- インタビュアー
- HATSの特徴について詳しく教えてください。
- 林
-
方向性としては、汎用的なロボット管理システムを目指しています。ロボット用の遠隔管理・遠隔制御機能だけでスタートしましたが、そこに複数台のロボットを連携させる機能やフリート管理の機能を増やしてきました。クラウドベースのロボット用の上位管理・制御ソフトウェアとして、自社のプロダクトを進化させているところです。
ROS(Robot Operating System)対応だと連携しやすいですが、メーカーさんからインターフェースに必要な情報をいただければ、ROSにかかわらず対応可能です。基本的には、インターフェースさえあれば、メーカーを問わず技術的には接続可能です。
- インタビュアー
- ロボットの完全自動化についてはどのように考えていますか。
- 林
-
自動化は将来的には完全な形で実現する可能性はありますが、それはそれほど早くは進まないと考えています。ある業務が自動化されても、また新しい業務が発生しますし、企業が競争していく中で常に新たな取り組みが生まれる。そういった余地はまだまだあると思います。
特に物理的な制約のあるロボット技術は、AIのような急速な進化は見込めません。全身の動作はかなり進歩しましたが、手の器用さに関するところは、まだまだ余地があります。
現場の自動化案件をやらせていただいていると実感するのですが、まだまだ人でやっている業務が多く、そもそも定常的な業務ではないものがたくさんあって、デジタル化も進んでいないという現実があります。人間の温かみや柔軟性が必要な場面が、想像以上に多いのです。

- インタビュアー
- 現在の事業領域はどのように選ばれたのでしょうか。
- 林
-
現在は特に物流・倉庫分野のロボットを対象に事業を展開しています。これは単純に事業としてどの市場がいいかという視点で考えた結果です。ロボット管理の分野は、ある面ではブルーオーシャンです。従来はシステムインテグレーター(SIer)が個別にその業界に合わせて用意していましたが、当社では、それをパッケージソリューションの形で代替しています。
でも、私たちが本当に力を発揮したいのはこれからです。今後は、フリート管理機能の充実、対応機種の拡大、アームロボット分野への進出などを視野に入れています。特に一般環境で使用される汎用性の高いロボットが増えてくると、当社の技術がより生きてくると考えています。
一般環境でより汎用性の高いロボットに必要な機能を伸ばしていくことで、データの再利用や、複数の人が複数の現場の複数種類のロボットを管理するような、より集約的な管理のニーズが生まれます。現状では個別開発でまだ対応できる範囲に収まっているものが多いですが、それが変わってくれば当社の真価が問われる時が来ると考えています。
多様性を活かした組織づくりこそ、イノベーションの源泉
キビテクの組織運営において特徴的なのは、メンバーの多様性だ。現在約50名の社員の大半がエンジニアで、外国籍の社員が多いこと、シニア人材の積極的な採用などが挙げられる。この組織づくりには、林氏の深い信念がある。

- インタビュアー
- 組織の多様性については、意図的に取り組まれているのでしょうか。
- 林
-
これは事業をよりよく回していくという目的もありますが、それ以上に私たちの価値観を体現するものです。ロボットエンジニアは採用が難しく、特に日本人の人材が採用市場にいる可能性が限られています。結果的に外国籍で日本に住んでいる方が多くなっています。これは当社だけでなく、ロボット業界のスタートアップ全体の傾向でもあります。
でも、彼らと働いていて実感するのは、日本のロボット技術に対する信頼の高さです。遠隔で面談して、就職が決まったから当社入社のために日本に移住するといったケースもあります。「日本でロボット技術を学びたい」「日本の技術力を世界に広めたい」という熱い思いを持った人たちが、世界中から集まってくれているのです。
また、年齢の多様性も重視しており、最高齢の方は後期高齢者に入るくらいの年齢でも、現役でとても元気に活躍しています。この方は電子回路の設計者で、若い頃から培った技術が今も生きています。年齢を重ねるスピードは人によって違うんだなと、心から感じます。
- インタビュアー
- AI技術との連携についてはいかがでしょうか。
- 林
-
AIによってエッジ側で自律的に制御できるものが増えてくるので、ロボットの汎用管理システムとAIは競合ではなく共存していく必要があると考えています。むしろ、ロボット用のAI技術を実際の現場のロボットに適用する際に、当社のシステムを通じて有効活用できるよう、プロダクトを発展させていきたいと思っています。
現在は大学との共同研究などを通じて、ロボットに適したエッジでの大規模言語モデル関連の技術開発と検証を進めています。技術の進歩は目覚ましいですが、最終的には人間の温かみが必要な場面が必ずあると信じています。
- インタビュアー
- 今後求めている人材はどのような方でしょうか。
- 林
-
ビジネス開発の人材は海外展開にこだわらず求めています。また、ロボットエンジニアも常に求めています。
ロボットそのものをやっていた方でなくても、例えばメーカーで電子機器や家電機器の設計開発をやられていた方で、早期リタイアして、スタートアップで働いてみようかなという方にも興味を持っていただいています。
実際の現場の自動化を多く実現していくことが当社の事業コンセプトです。自分のやっていることが社会で実際に使われているという実感を得たいエンジニアの方にとっては、当社は魅力があるのではないかと思います。
私たちと一緒に、技術で社会を変える喜びを分かち合える仲間を求めています。
誰もが技術の恩恵を受けられる社会を未来世代に残す
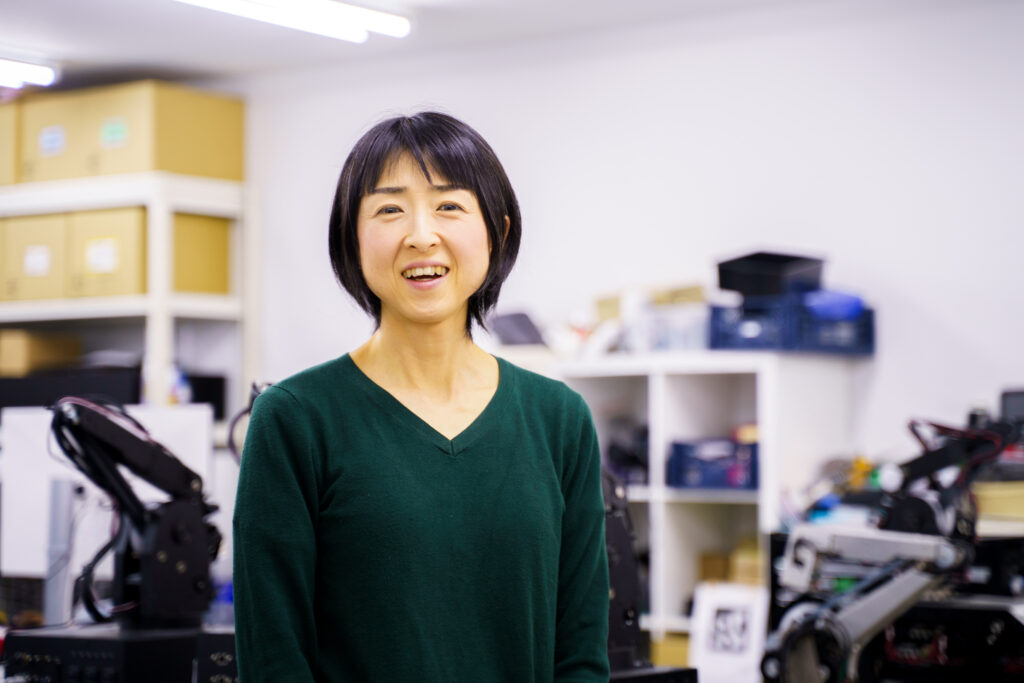
インタビューの終盤では、製造業やロボット産業全体への展望についても語ってくれた。林氏が描く未来は、単なる省人化や自動化ではなく、人間とロボットが調和して共存する社会だ。その根底には、母親となった林氏の、子供たちへの深い愛情がある。
- インタビュアー
- キビテクが目指す未来を教えてください。
- 林
-
当社が目指すのは単なるオートメーション化ではなく、産業の持続可能性を高めながら、スモールフィットな自動化を実現することです。特に中小企業など、これまで大規模な自動化投資が難しかった現場にも、ロボット技術の恩恵を広げていきたいと考えています。
現在は主に物流・工場の自動化支援に注力していますが、将来的にはより広範な社会課題に取り組むビジョンを持っています。特に、ロボット技術による労働代替が進む中での格差是正や、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。
中堅企業との共同開発の経験も豊富なので、お客様の現場での効率化に直接貢献できます。倉庫や工場をお持ちの製造業や物流業の事業者さんとのつながりを求めています。
ロボットの展示会などで魅力的に見える製品も、実際の現場ですぐに使えるわけではないという理想と現実のギャップがあります。そのギャップを埋め、比較的安いコストで現場への適用を実現できるケースが多いのが当社の強みです。
ロボット技術で未来世代が抱えるであろう問題を解決することにつながる取り組みをしたいと思っています。私が子供を産んで気づいたのは、技術者として、母親として、そして一人の人間として、未来世代に何を残せるかということです。ロボット技術によって人間の可能性を広げ、誰もが技術の恩恵を受けられる社会を作りたい。それが私たちの使命です。
- インタビュアー
- ありがとうございました。
技術者の純粋な好奇心から始まった挑戦が、母親としての愛情を経て社会的使命へと昇華された林氏の歩み。それは、テクノロジーが真に人々の幸福に貢献するためには、技術的な優秀さだけでなく、深い人間理解と社会への洞察が不可欠であることを物語っている。
ロボット技術の専門家として、またビジョナリーな起業家として、林氏はテクノロジーと人間性の調和を追求し続けている。人間とロボットが共存する未来社会の実現に向けて、キビテクの取り組みは日本のロボット産業に新たな可能性を示すとともに、世界からも注目される革新的なソリューションとなっていくだろう。
こちらの記事はに公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。